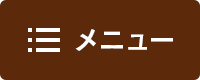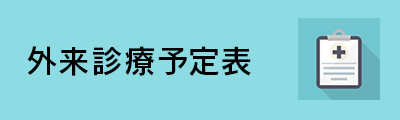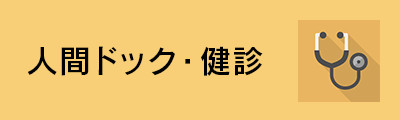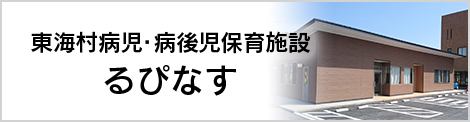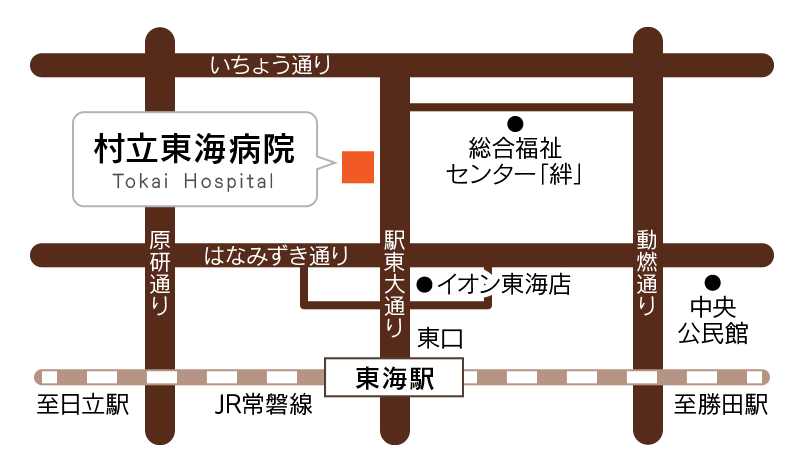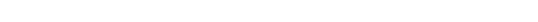1月の行事食は「お正月」でした

新年あけましておめでとうございます
幸多き新春をお迎えのこととお喜び申し上げます
今年も美味しく笑顔になれる食事をお届けできるよう栄養室一同頑張っていきたいと思います
第15回健康公開講座を開催しました
令和7年11月25日(火)に第15回健康公開講座を開催しました。
今回は、「未来を守るワクチン講座~あなたと家族の健康のために~」と題して、内科の稲葉医師が「インフルエンザ」「帯状疱疹」「肺炎球菌」「コロナ」「HPV」の予防接種についてお話しいたしました。


12月の行事食は「クリスマス」でした
12月24日の昼食は「クリスマス」をテーマとしたメニューでした。
常食◆ハンバーグプレート、マカロニソテー、シーザーサラダ、クリスマスデザート

今年も残りわずかとなりましたが、どうぞよいお年をお迎えください。
11月の行事食は「七五三」でした
献立(常食)◆ちらし寿司、茶碗蒸し、なます、すまし汁

子供の健やかな成長を祝い祈願する七五三は、その名の通り3歳、5歳、7歳で行われます。
3歳・5歳・7歳を節目とした理由は、暦が中国から伝わった際に奇数は陽、つまり縁起がいいとされた為で「3歳で言葉を理解し、5歳で知恵がつき、7歳で乳歯が生えかわる」という成長の節目の歳の為ともいわれています。
今回はお祝いと言うことで縁起を担ぎ、ちらし寿司にしました。
見た目も華やかなちらし寿司は、皆様から「おいしかったよ」という感想をいただけました。
10月の行事食は「ハロウィン」でした
常食献立◆カレーピラフ、じゃがいものトマト煮、ブロッコリーのドレッシング和え、かぼちゃババロア

ハロウィンの起源は、古代ケルト人の「サウィン祭」と呼ばれる収穫祭にあるとされています。
この祭りは夏の終わりに行われ、収穫を祝うとともに祖先の霊を迎え、悪霊から身を守るという意味が込められていました。人々は火を焚いたり仮面をかぶったりして、霊や災いから身を隠そうとしていたといわれています。
最近では日本でもハロウィンはイベントとして定番となっており、仮装をしたり、かぼちゃを使った料理を食べたり、お菓子を配ったり食べたりすることが主流となっています。
当院の昼食では、カレーピラフやかぼちゃババロア、ハロウィンカラーのオレンジや黄色系を取り入れたメニューにしました。
「おいしかったよ」「病院でハロウィンが楽しめるなんて思わなかった」など、患者さんから喜びのご意見をいただきました。
9月の行事食は「敬老の日」でした
「敬老の日」は 1966年(昭和41年)に制定されました。
かつては、毎年9月15日が「敬老の日」と定められていましたが、2003年から9月の第3月曜日に変更されました。
祝日法では「多年にわたり社会に尽くしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う日」とされています。
常食献立◆赤飯、すまし汁、天ぷら、茶碗蒸し、茄子のしそ和え

今年も皆様の健康と長寿を願い、心を込めて作りました。
秋暑厳しい毎日ですが、体調を崩されませんよう、ご自愛ください。
8月の行事食は「処暑」でした
献立(常食)◆ 鮭とミョウガのちらし寿司、含め煮、トマトとオクラの和風和え、抹茶羊羹

処暑とは、1年を二十四等分した二十四節気で「暑さが和らぎ、厳しい暑さが峠を越す頃」をさします。
今回の献立は、胃腸を整え夏の疲れを癒す旬の食材を取り入れました!
処暑を過ぎ、日中はまだまだ暑いですが朝晩はやや気温が下がってきたように感じます。
季節の変わり目は寒暖の差から、疲れが出やすく体調を崩しやすいので、毎食きちんと食事を取り、ご自愛ください。
7月の行事食は「七夕」でした
献立(常食)◆ 七夕そうめん、白身魚の磯辺揚げ、オクラの焼き浸し、水ようかん

7月7日は「七夕(たなばた)」の日。
織姫と彦星が年に一度だけ会えるという伝説があり、日本でも短冊に願いごとを書き笹に短冊を飾ったことがある方も多いと思います。
そうめんは七夕の行事で食べられることが多いですが、元々中国で七夕の日に小麦や米粉を練って縄状にした「索餅(さくべい)」に由来し、「無病息災を願って」食べたと言われています。
そこから時が経ち、日本では索餅がそうめんへと変わっていきました。
そうめんはご飯やパン、うどんに比べエネルギーや食塩量が高く、今回当院の食事でも提供した天ぷら等の揚げ物とあわせがちとなりますが、夏バテし食欲が落ちたときにもさっぱりと食べやすい物でもあります。
今回当院でも患者さんから
「さっぱりして良いね」 「暑いから毎日でもいいよ」
と、お声かけいただきました!
そうめんと共に野菜を食べたり、揚げ物の量に気をつけたりしながらバランスをとった献立にしましょう。
今年も暑さが厳しいですが、どうかお体にお気をつけてお過ごしください。
第14回健康公開講座を開催しました
6月25日(水)に第14回健康公開講座を行いました!
今回は「骨粗しょう症」をテーマに内科の荒井医師が講師を務めました。

・どんな病気なのか?
・どんなことに気をつけなくてはならないのか?
・どんな予防法があるのか?
など骨粗しょう症を知ってもらうための場となりました。
これからも地域の皆さまが健康づくりを意識して生活していただけるよう、このような講座を定期的に開催していきたいと思います!
6月の行事食は「入梅」でした
献立(常食)◆ご飯、メバルのバター醤油焼き、茶碗蒸し、ビーンズサラダ、紫陽花ゼリー

入梅とは、暦の中で梅雨入りの頃を表す言葉で、今年は6月11日です。また、今年の関東の梅雨入りは6月10日頃と気象庁より発表がありました。
日本では昔から季節や節目に合わせて行事食を食べる習慣がありますが、入梅の時期ということで、今回の行事食は、あじさいを表現したお食事を提供させていただきました。
梅雨の時期は、心身ともに不安定になりやすい時期ともいえます。健康維持のためには、バランスのよい食事・適度な運動・睡眠など、生活習慣に気を付けましょう。